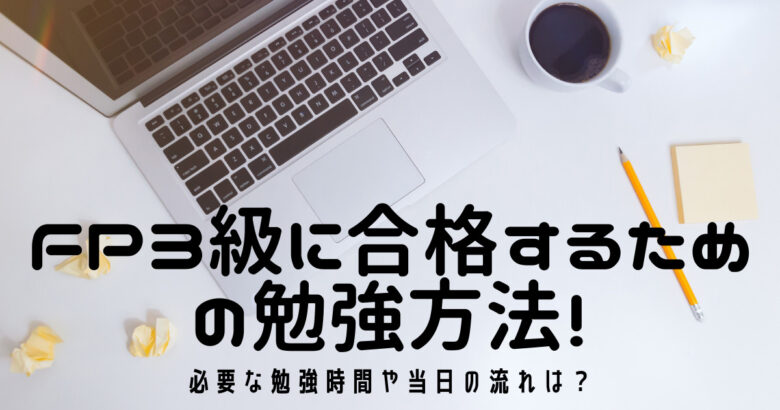こんにちは、みーとのりおです。
早速のご報告ですが、この度私たち二人そろって
「FP技能士3級(資産設計提案業務)」の資格試験に合格することができました!
今回は
について、私たちの体験をもとにお話していきます。
※この記事はみーがメインで書いていますが、ゲストでのりおも登場しますよ!
FP技能士について興味がある人や、これから節約や資産形成について力を入れていくためにお金に関する知識をつけたいと考えている人はぜひご覧ください!
どうしてFP技能士試験を受けようと思ったの?
結論からいうと、とにかく「お金のことがもっと知りたかったから!」です。
FP技能士とは、ファイナンシャル・プランニング技能士の略称です。
これからの将来に向けてのライフプランや現在の資産状況をもとに、それぞれの目標を達成するための資金計画を立てることをファイナンシャル・プランニングといいます。
FPの勉強を行うと得られる知識は大きく6分野あります。
私たちは、いざ節約だ!運用だ!資産形成だ!と意気込んでいたにもかかわらず、基本的なライフプランの立て方や、資産状況の把握方法、保険や年金、税金についての知識が十分に備わっておらず… ましてや不動産や相続についての知識なんて皆無でした。 そんな中、ある日のりおが「FPの試験を受けようと思う!」と提案してきたので、 私は二つ返事で「いいじゃん!私も受ける!!」と答えて、二人してFP試験を受けることにしたのです。 FP技能士の勉強で学ぶことができる範囲は、先ほども上げた6分野です。 3級の試験は毎年3回(1月・5月・9月に)行われています。 試験は学科と実技の二つがあり、どちらともに合格することで資格取得となります。 実技試験には3つの種類があるので、申し込みをする際には自分が受けるところを一つ選ぶ必要があります。 FP技能士3級実技試験の種類 〇金財:個人資産相談業務 ⇒リスクマネジメント以外の5分野から出題される 〇金財:保険顧客資産相談業務 ⇒保険分野の出題が多い (保険関係の業務に就職したいと考えている人や、保険会社で働いている人向け) 〇日本FP協会:資産設計提案業務 ⇒6分野からまんべんなく出題される 金財・日本FP協会ともに試験の合格ラインは、学科・実技それぞれ6割以上の正解が必要です。 ざっくり計算すると、以下の正解数で合格ラインに届くことになります。 【金財】 ・学科:60点満点で36点以上(1問1点:全60問中36問以上) ※学科は日本FP協会と共通です。 ・実技:50点満点で30点以上(3点が10問、4点が5問:全15問中9~10問以上) 【日本FP協会】 ・学科:60点満点で36点以上(1問1点:全60問中36問以上) ※学科は金財と共通です。 ・実技:100点満点で60点以上(1問5点:全20問中12問以上) 私たちは全体的に知識を得たいと考えたので、9月に行われる日本FP協会:資産設計提案業務を受けることにしました。 問題内容も、一般家庭のキャッシュフロー表を仮定したものや、バランスシートから資産額を読み解くもの、新聞などでの株価欄の見方が学べるものもあり実際の生活に置き換えて勉強していくことができます。 受験料は、6,000円(学科3,000円・実技3,000円)です。 ※支払手数料は自己負担となります。 試験を受けると決めてから、まずはテキストと問題集を購入しました。 私たちが購入したのは、以下の「みんなが欲しかった!」シリーズのFP3級の教科書・問題集です! 教科書はフルカラーで分かりやすく、問題集ともつながっているのですぐに復習できてとても効率よく勉強を進めることができました。 これを1冊ずつ購入し、二人で共有しました。 勉強方法 私たちが受ける試験は9月だったのですが、本格的に勉強を始めたのは7月頃でした。 私は基本的に、以下の流れで勉強を行っていました。 みーの勉強方法 ①~⑤の繰り返しでテキストを少しずつ進めていきました。 テキストを最後まで終えるとまた1つ目の分野に戻り2周目に入ります。 (私は2周目も終え、3周目の途中で試験直前になってしまいました。) 当たり前ですが、1周目より2周目・3周目のほうが頭に入ってくるので、きちんと内容を理解したうえで問題を解くことができます。 私はテキストの最初から順番通りに勉強を進めましたが、自分の興味のある分野から取り掛かる方法も良いかもしれません。 9月に入り試験まで残り2週間を切ってからは、過去問を中心に解き、問題の出題パターンに慣れることに重点をおいて勉強を行いました。 ネット上で過去問を解くことができるサイトなどもあり、移動中でも手軽に勉強できたことは本当にありがたかったです。 合わせて、実際の試験時間内で解くことができるか、自分でタイマーをセットして模擬試験も行いました。 試験直前はひたすら過去問だけを解いて、おおかた合格ラインである6割以上の正解率を取れるようになっていました。 勉強時間 ※毎日の勉強時間をきちんと記録していたわけではなく、あくまで私の記憶の中から引っ張り出して計算したものになるのでご了承ください。 7月から勉強を始めてどのくらいの時間を勉強に充てたのかというと、 平日:約1時間/日 1か月の平日22日間 休日:約0.5時間/日 1か月の休日9日間 総勉強時間は 平日約52時間+休日約10.5時間=約62.5時間となります。 体調の悪い日や気分が乗らない日は勉強をさぼってしまうこともありました。 逆にものすごくやる気になって1日に3時間以上も勉強したり、はたまたすぐに飽きて30分ほどで終えてしまった日もあったので、お恥ずかしながら毎日きちんと1時間ずつ勉強していたわけではありませんでした。 これを短いととるか長いととるかはそれぞれだとは思いますが、私はこのくらいの勉強時間で試験に向けて十分に理解しながら勉強することができました。 勉強方法 のりおが本格的に勉強を始めたのは、みーより遅く、試験1ヶ月前の8月中旬からです。 勉強手順は、以下の流れで行いました。 のりおの勉強方法
試験の概要
勉強方法や勉強時間は?
【みーの場合】
1時間×52日(7月~試験まで)=52時間
0.5時間×21日間(7月~試験まで)=10.5時間 ほどであったと記憶しています。【のりおの場合】
この繰り返しですべてのセクションを終え、2周目は問題集にのみ取り組みました。
2周目を終えた時点で間違えた問題に丸印をつけ、3周目は2周目に間違えた問題のみを解いて試験に挑みました。
ここまで勉強すると、試験を受ける前から、おそらく合格できるだろうと自信を持つことができました。
みーと大きく違う点は②「最も知識を持っているセクションからテキストを読む」、④「間違えた問題だけもう一度解く」の2点ですね。
のりおは勉強開始時に取り組みやすくすることと、分からない問題を効率よく無くすことを重要視しているため、このような勉強法をとってみました。
具体的には、個人的な趣味で以前調べたことがあった、税や金融商品、保険から勉強を始めています。
自分がとっつきやすいセクションから勉強を始めることで、スムーズに取り組みむことができるため、この方法は非常にお勧めですよ!
勉強時間
1か月間勉強した総時間は下記の通りになります。
平日:約0.5時間/日 1か月の平日22日間
0.5時間×22日(8月中旬~試験まで)=11時間
休日:約3時間/日 1か月の休日9日間
3時間×9日間(8月中旬~試験まで)=27時間
総勉強時間は 平日約11時間+休日約27時間=約38時間
のりおもみー同様に1日の勉強時間にばらつきがあったため、あくまで記憶上の平均値を用いての計算になります。
のりおとみーで勉強時間に開きがあるのは、①事前知識があるか、②どこまで勉強するか、の違いです。
のりおは事前知識があったため、勉強時間はみーの60%ほどに抑えてることができましたが、残念ながら試験の成績はみーの方が高得点でした😭
試験当日の流れ
当日のスケジュール
〇学科試験10:00~12:00(120分)※事前説明のため9:40集合
〇お昼休み12:00~13:10
〇実技試験13:30~14:30(60分)※事前説明のため13:10集合
※試験はすべてマークシート式です。
当日必要な持ち物
のりおは、試験に必要な本人確認書類を忘れてしまい、後日の書類提出を慌てて行うこととなります。会場では顔写真をつけることで試験を受けることができ、本当に本当に助かりました。 みなさんは、忘れ物がないように出発前にきちんと持ち物を確認しましょうね!
時間には余裕をもって出発し、ひたすらスマホで過去問を解きながら移動。
同じ電車に乗っている人の中には、FP3級のテキストを確認している人がちらほらいました。
9:20到着
会場はすでに多くの人で埋まっていました。
まだ席に着くことができないので、テキストを確認しながら待ちます。
お手洗いには時間に余裕をもって行きましょう。 特に女子トイレはギリギリになると長蛇の列になるので要注意です!
9:30開場
自分の席に着き必要なものを机の上に準備していきます。
私は受験票・マイナンバーカード・シャープペンシル2本・消しゴム1個・計算機・腕時計を用意しました。
また、飲み物を置くことも許可されていたので、ペットボトルなどを机の上に出している人もいました。
学科試験は120分ありますが、60分経過後から終了時間の10分前までは自由に退室可能となっています。
60分経過後すぐに退室した場合、そのままお昼休みに入るので、最大で11:00~13:10までの自由時間となります。
FP3級の学科試験は見直しまで入れても結構時間が余ります。
60分経過したら試験官から退室の案内がされるので、自分の荷物をまとめて、解答用紙を提出してそのまま退室します。
一度外へ出てしまうと、中には戻れないのでしっかり見直し等を行い、後悔のないようにしてくださいね。
11:00~ お昼休み
私たちも60分ですぐに退出したので、そのままお昼休みに入ります。
どこかお店へ食べに行っても良かったのでしょうが、無駄に会場を離れることがもったいないと思ったので、家からご飯を持参して会場のすぐ外で食べました。
同じようにされている人もたくさんいて、なんだかライブの開場を待つたくさんの人がドームの周りに座り込む風景を思い出しました…。
ご飯を食べた後は実技試験に向けての最後の確認を行い、お互いに問題を出し合ったりして過ごしました。
ここでもお手洗いには時間に余裕をもって行きましょう!
13:00開場
再度自分の席に着き、必要なものを机の上に準備していきます。
内容は学科試験の時と同じです。
実技試験は60分で、途中退室はありません。
終了したら、試験官に解答用紙を回収されますので、自分の荷物をまとめたりして案内があるまで待ちます。
案内があったら、指示に従って退室して試験はすべて終了です。
私たちが家に帰ってきたのは16:00頃。
会場から家が離れていることもあり、それなりに時間がかかってしまいましたが、これから試験を受けられる方は、丸一日スケジュールを開けておく必要があることを覚えておくと良いかもしれません。
私たちは帰宅してから、17時に公式ホームページにアップされた模範解答で自己採点を行いました。
その結果、自己採点では合格圏内!
その日の夕飯を気持ちよく食べることができました。
合否発表まで
これまで勉強しっぱなしの毎日だったため、久しぶりに勉強をしなくてもいいのんびりした日々を1週間ほど過ごしたのち、
私は事前の自己採点で合格圏内だったので、続いてFP技能士2級を受けることに決めました!
早速2級のテキスト・問題集を購入して勉強準備は万端です。
【追記:2022/02/06】2022年1月23日に無事FP2級の試験を終えました。FP2級に向けての勉強方法や当日の様子についてもまとめてみましたので、ぜひご覧ください!
こちらもCHECK
-
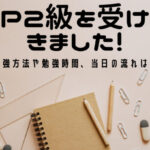
-
FP2級を受けてきました!勉強方法や勉強時間、当日の流れは?
続きを見る
のりおは、仕事上必要な資格試験を控えているので、試験はいったんお休みです。
日常生活に活かすにはFP3級でも十分に知識がついたので、今後2級を受けるかは考え中だそうです。
そして、つい先日の2021年10月25日にネット上で結果発表がありました。
二人とも無事合格!!
数日後には結果通知書と合格証書が自宅に届き、一安心です。
さいごに
FP技能士3級の資格勉強をしてみて、今までこれだけのことを知らずに社会人生活を送っていたのかと驚いたと同時に、このタイミングで知ることができてよかったと思いました。
自分たちが支払っている保険料や税金、将来受け取るであろう年金についての知識や、まったく知らなかった不動産や相続の知識を得ることができたのは私の中でとても大きかったです。
仕事だけではなく、自分自身の人生に活かすことができるのでありがたいですね。
資格試験を受けるかどうかは別として、勉強だけでもしてみるといいかもしれません。
少しでも興味がある人は、ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。
まだまだ先になりますが、私が無事にFP技能士2級に合格することができたのかどうかについても報告しますので、よければそちらも参考にしてみてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。